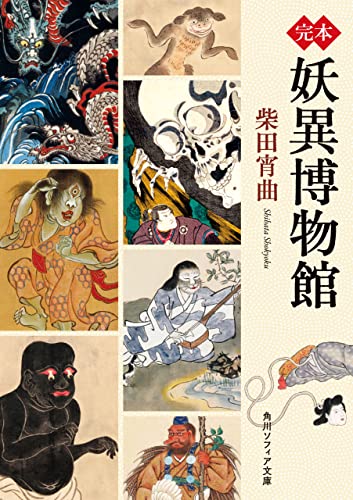読了日2023/01/15。
冒頭の第一首「体温計くわえて窓に額つけ「ゆひら」とさわぐ雪のことかよ」は、中学国語教科書にも採られている。三十一文字の僅かな字数で、場面と人物関係を鮮やかに喚起する手際は、短編小説の佳品のようだ。一首毎に背後の物語を感じさせ、また解説で瀬戸夏子氏が述べるように、本書全体の配列も恋愛→別れ→新たな出会い→死というストーリーを構成している。まるで歌から、それを詠んだ状況を説明した詞書が発展して歌物語となった伊勢物語のように。作中の「ほむ」と現実の作者は、業平と昔男が異なるように、同一でなく歌の主人公を演じている。
「桟橋で愛し合ってもかまわないがんこな汚れにザブがあるから」「天使にはできないことをした後で音を重ねて引くプルリング」という強烈なエロスは、「「海にでも沈めなさいよそんなもの魚がお家にすればいいのよ」」で終わる。手紙魔まみは「おしっこを飲むとかそういうのじゃないのまみが貴方を好きな気持は」という爛漫さで「ほむ」を救う。「「血液に型があるの?」と焼きたてのししゃもみたいな事故車の前で」かつて第三者として見た惨劇の現場に、次は主人公となる。「きらきらと海のひかりを夢見つつ高速道路に散らばった脳」。
穂村弘は吉田悠軌『一行怪談』の解説も書いていたが、確かにショート・ショート的な怖さは通じるかも知れない。「恐ろしいのは鉄棒をいつまでもいつまでも回り続ける子供」「血まみれの歯ブラシを手に近づけばぴたりととまる夜の噴水」。